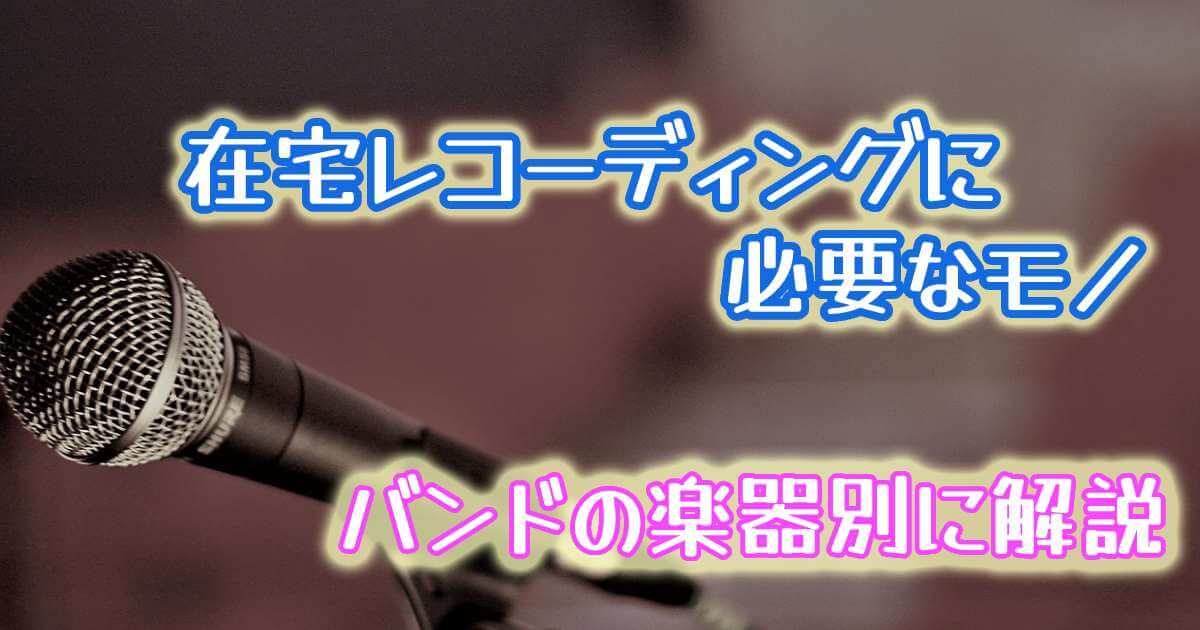こんにちは、さにれたです。
このブログではライブ配信のコツや始め方、機材についての初心者向けの解説
そして、音楽活動のコツ、などをまとめています。
今回は、Twitterから寄せられた以下の質問にお答えします。

宅録するのに必要なモノってなんだろう?

楽器や状況によって異なるから細かく解説していくよ!
今回は『在宅レコーディング=宅録』に必要なモノを解説していきます。バンドの楽器別に必要なモノを記載しますので、DTMや在宅での製作を本格的にやりたい人から、レコーディング費用を浮かすために最低限の予算で十分な品質の機器を用意したい人にもお勧めの記事です。
なお、管理人は20曲以上の楽曲リリース経験があり、そのうち半数は宅録での製作です。その経験から詳細に必要なものを紹介していきます
- エレキギターやベースの宅録で必要なもの
- エレクトリックピアノの宅録で必要なもの
- ボーカルやマイク録りする宅録で必要なもの
- ドラムの宅録で必要なもの
※宅録とレコスタの比較が気になる方は以下の記事もチェックしてみてください。
共通して必要な道具

まずはどの楽器でも必要な道具から解説していきます。
PCとDAWソフト
まず、PC(パソコン)は必須です。そして、DAWソフト(作曲やレコーディングができるソフト)を用意します。これが一番予算がかかります。
PCはDAWソフトが快適に動くスペックのものが必要です。
1トラックレコ―ディングする程度であれば、PCでスペックは以下のようなクラスがあれば十分でしょう。
- CPU・・Core i5
- メモリ(RAM)・・8GB
- ストレージ・・512GB
このあたりのスペックで、PCに十分な空き容量があればとりあえず大抵のDAWは動きます。
ただ、これは最低限です。DTMで簡単なデモを作ったり、録音をする程度であれば問題ないですが、本格的な作曲や編集をする場合は以下のようなスペックが必要になります。
- CPU Core i7以上
- メモリ(RAM) 16GB以上
- ストレージ SSD512TBのメインストレージ+2TBの別ストレージ(SSDだとより良い)
これぐらいのスペックが欲しいです。ミックスマスタリングを出来るようになりたい方や、やる予定がある方はハイスペックなモノを選びましょう。
バンドに一人はこのクラスのスペックのPCと編集スキルがある人がいたら活動がスムーズです。

うーん、おススメの買い方やサイトはあるかなぁ

ハイスペックは新品でBTOでの購入、とりあえず録音だけしたいなら、中古PCだと手軽で良いかな
パソコンは、上にあげた最低限のスペックでも良い値段することが多いので、中古PCで用意するのも手段です。
たとえばPC WRAPだと、7日間の送料無料で返品ができたり、3年の保証のモデルもあるので中古PCでも安心して購入できます。ただ、中古PCだと512GB以上のストレージがあるモデルが少ないので、サイト内の検索欄で512GBなどで検索してソートするのが良いですね。容量が少ないと詰みます。
逆に、今後を見据えて本格的なDTM用のPCを用意したいのであれば新品にしましょう。BTO(ビルド・トゥ・オーダー)パソコンは追加料金でカスタマイズして注文できるので、DTMに合ったPCを選べます。
直近でコスパの良いBTOサイトが見つからなかったので良さげな商品リンクを貼っておきます。大体10~20万ぐらいでそろえて十分な品質です。それ以上は予算をかけすぎかもしれません。
オーディオインターフェイス
オーディオインターフェイスはマイクやギターシールドなどをPCにさせないので経由する役割の機材だと思ってください。音質にも関わってくるので、しっかり選びましょう。スペックは24-bit/192kHz以上に対応しているものを選びましょう。
接続数(in)に関しても、2つ以上のものを必ず選びましょう。1つから4つぐらいが宅録でよく使われる範囲ですが、inが1つだとステレオ録音したり、複数マイクを立てるなど、やりたいことが増えたときに対応できなくなります。
そしてファンタム電源搭載のものを選びましょう。コンデンサーマイクを使う場合に必須になってきます。
ちなみに、マイクプリアンプという内臓のパーツで音質が変わるのですが、1~2万円ぐらいの有名ブランドのものであれば誤差程度です。極端に安い謎ブランドのものを買わなければOKです。
↑管理人のオススメオーディオインターフェイスです。CubaseAIがつくうえ、音質も十分なUR22はとてもおススメです。
DAWソフト
DAWソフトとは作曲ソフトのことです。Cubase, logic, Pro tools, studio one, ABLETON LIVEなど様々な種類があり、無料版から最高グレードだと5万円以上するものもあります。
録音で必要な品質の24bit/192kHz以上のサンプリングレートに対応しているものを選びましょう。
ちなみに、先ほど紹介したオーディオインターフェイス、UR22に付属しているソフトCubase AIは、64bitのオーディオエンジン、192kHzまでのサンプリングレートに対応していて、上位モデルのCubase Proに変えるのも格安でグレードアップできるのでお勧めです。(管理人はCubaseユーザーです)
ちなみに、DAWソフトの個人的な印象を下記にまとめました。参考程度に見てみてください。
- Cubase・・打ち込み作業に強い。ユーザー数が多く解説動画が多い。最上位モデルのProになるとピッチ補正ソフトが付属する。コード補助など作曲アシスタントも充実。バンドル音源がしょぼい。
- logic・・ソフトにバンドルされている音源やエフェクトが優秀。追加のプラグインを増やさなくても品質が高いものが作れる。ソフト自体も安いのでかなりコスパが良い。Mac専用でWindowsで使えない。
- Pro tools・・レコーディングの業界標準ソフト、これが使えるかどうかで音楽の仕事が増えるともいわれる。とにかくレコーディング作業周りに強い。月額課金(サブスク)で高い。
- studio one・・比較的新しめのDAWソフト。レコーディング作業よりのイメージだが詳しく知らない。最上位モデルでもかなり安い、動作も軽くてスペック低いPCにも優しい印象。他DAWと比べショートカットキーのカスタマイズが細かくできる。ユーザーが少ないため何かあった時に情報が少ない。
- ABLETON LIVE・・サンプリングやループに強く、ヒップホップなどのトラックメーカーが愛用しているイメージ。もちろんレコーディングや打ち込みもできる。標準搭載のエフェクトも優秀、特にリバーブは愛用者が多い。スコア(楽譜化)機能がない。安定性に欠け、ソフトが落ちる率が他DAWより高めの印象。
と言った感じです。どのソフトも使い方を覚えるまでは大変ですが「ソフト名 レコーディング 方法」とかで検索したらまぁ何とかなります。宅録だけなら何でもOKです。DTM打ち込みを本格的にやるならlogicかCubase、トラックメイカーでの作業が増えそうならABLETON LIVE、レコーディングの仕事を将来考えるならPro tools選ぶとよいかと思います。
以上が宅録に必要な、共通の道具の解説でした。
次のページではエレキギター・エレキベースの宅録に必要な物を解説していきます。